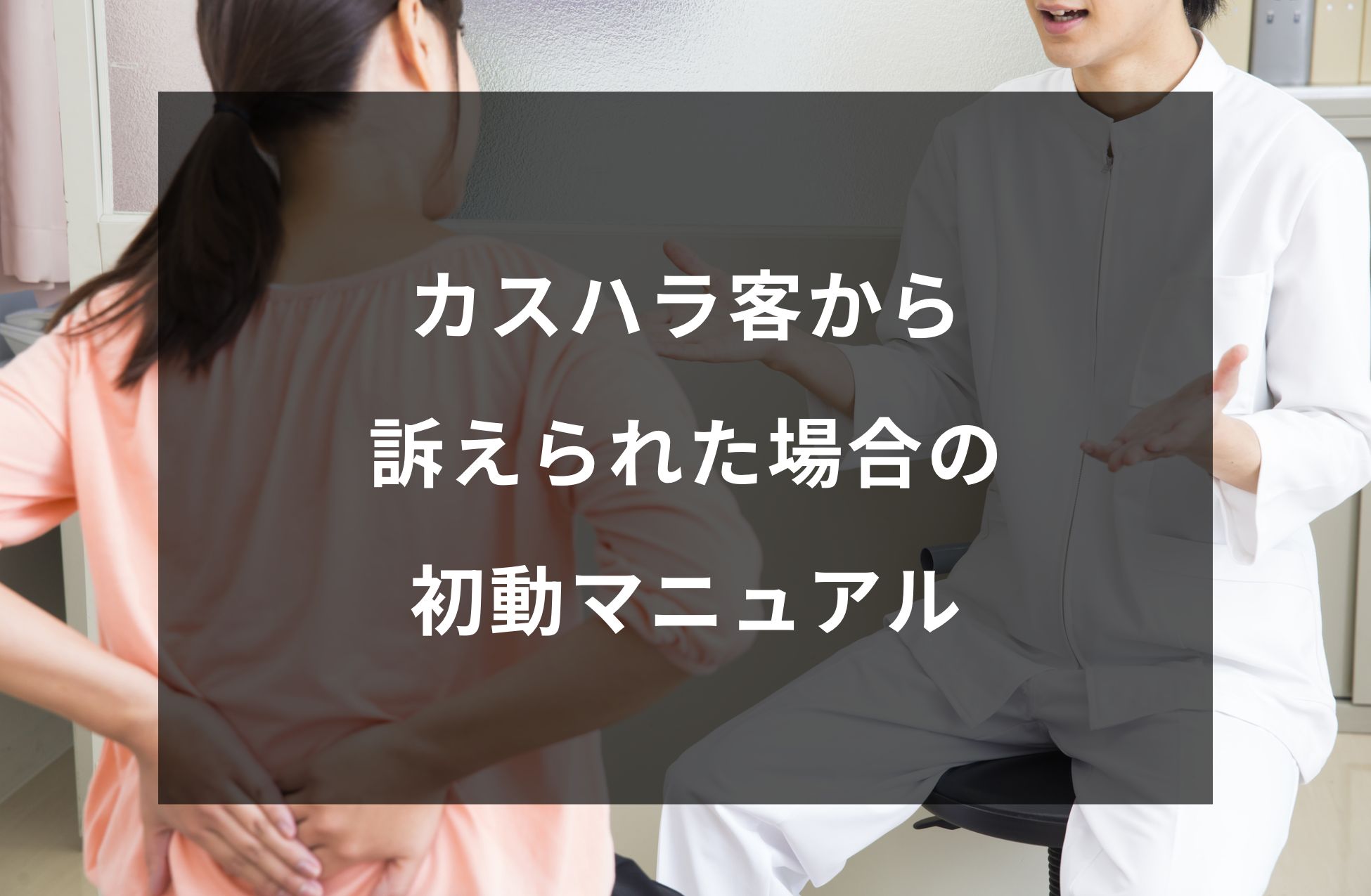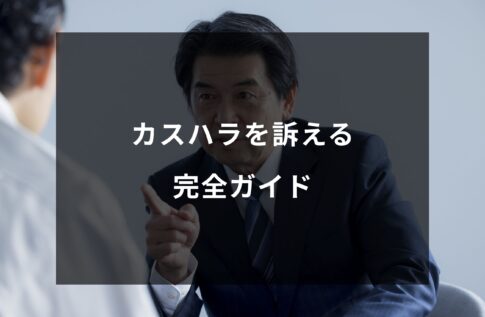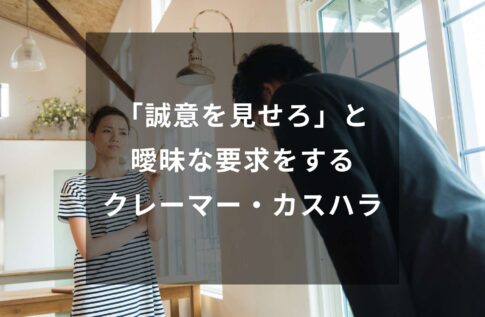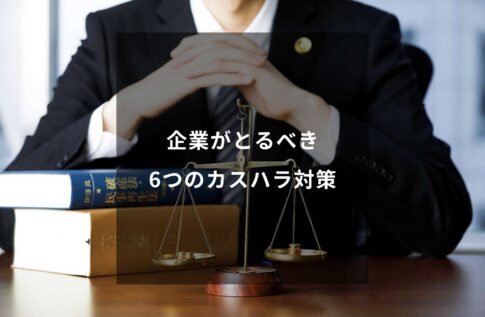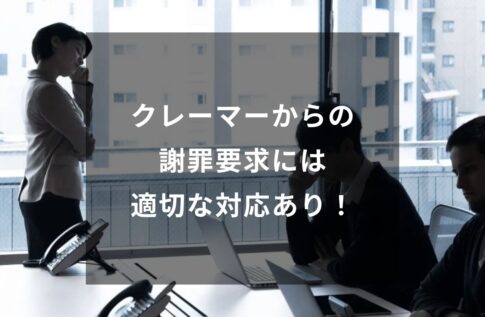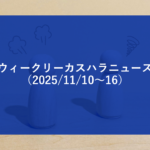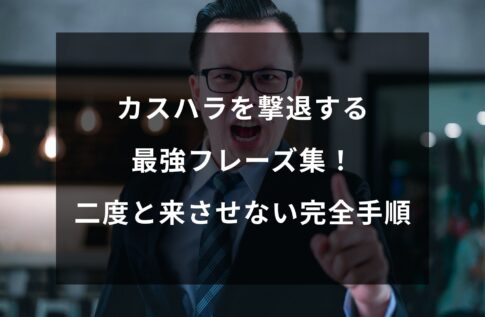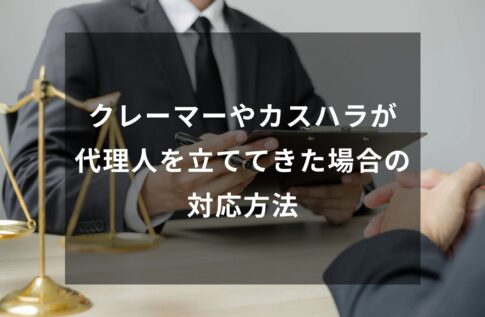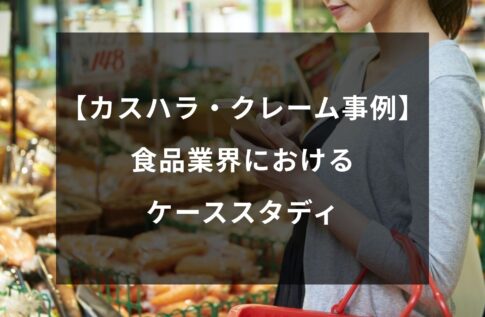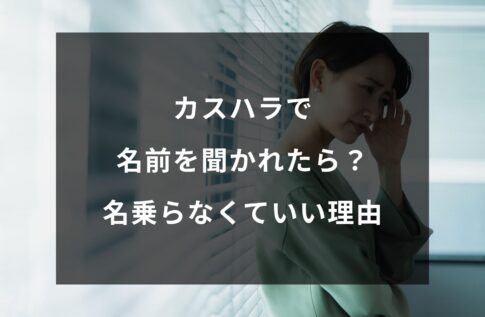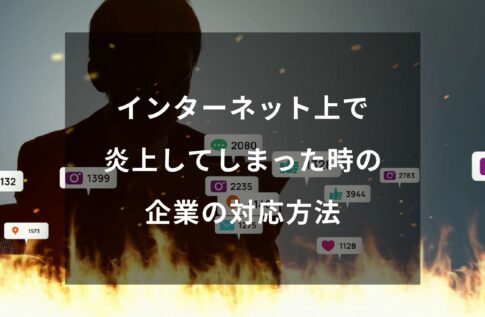「お前の態度はなんだ、精神的苦痛を受けた! 訴えてやるから覚悟しろ!」など、 理不尽な要求を繰り返す顧客に対し、毅然と対応した結果、逆に「法的措置」をチラつかされ、恐怖を感じていませんか?
「本当に裁判になったらどうしよう……」「会社の評判に傷がつくのでは?」 そんな不安を抱える担当者の方へ、まず結論をお伝えします。
過剰に恐れる必要は、全くありません。
なぜなら、カスハラ加害者が口にする「訴えてやる」の9割は、自分の要求を通すための単なる脅し文句(ハッタリ)であり、法的な効力を持たないケースが大半だからです。
しかし、だからといって放置は厳禁です。たった一度の初動ミスで、不当な要求に屈してしまうリスクもあります。
この記事では、法律事務所の専門家視点で、以下の問題を徹底解説します。
- 相手の発言に「法的根拠」があるかどうかの判断方法
- 万が一、本当に訴状が届いた時の「現場の正しい行動」と「費用感」
- 従業員の安全を確保し、二度と怯えさせないための組織的な対策
あなたが抱える恐怖は「見えない敵」への恐怖です。法律というライトで照らせば、恐るるに足りません。この記事で、自社と労働者を守るための「正しい武器」を手に入れてください。
カスハラ・クレーム対応に
お悩みの方は
お気軽にご相談ください
経営者様・会社様専門の相談窓口となっております
目次
カスハラ客の「訴えてやる」の9割はただの脅し

相手が激昂し「訴訟するぞ!」と叫んでいる時、現場はパニックになりがちです。しかし、まずは深呼吸をして冷静になってください。
実務上、クレーマーが実際に訴訟を起こす可能性は極めて低いです。彼らの目的は裁判で勝つことではなく、訴訟という言葉であなたを脅し、謝罪や金品を引き出すことにあるからです。
ここでは、なぜ彼らの主張が法的に通らないのか、その理由を3つの視点から説明します。
そもそも「態度が悪い」だけで損害賠償請求は成立しない
クレームを出す顧客が最もよく挙げるのが、「店員の態度が悪かった」「誠意がなかった」という点です。しかし、「態度が悪い」という理由だけで、法律上の損害賠償請求が認められることはまずありません。
法律の壁(不法行為の成立要件)
日本の法律(民法709条)で損害賠償を請求するには、以下の3要件が必要です。
- 故意または過失があること
- 他人の権利を侵害したこと
- 具体的な損害が発生したこと
「希望通りの対応をしなかった」のは接客上の不満に過ぎず、「権利の侵害(違法行為)」には当たりません。
また、「精神的苦痛を受けた」という主張についても、裁判で認められるハードルは非常に高いです。「診断書が出るレベルの重篤な精神障害」と、その原因が「企業側の行為のみにある」という因果関係を客側が証拠をもって証明しなければなりません。
単なる言い掛かりレベルで訴訟を起こしても、客側が勝てる可能性はほとんどない、これが実務上の事実です。不当な請求の妥当性は低いと判断しましょう。
「民事」と「刑事」を混同するクレーマーの心理
クレーマーは、法律事務所に相談する手間をかけずに、法律知識が曖昧なまま勢いで脅してきます。よくあるのが、「民事(訴訟)」と「刑事(警察)」の混同です。
- 損害賠償や慰謝料などを請求する個人間の手続き
- 警察は「民事不介入」の原則があり、関与しません
- 犯罪行為を取り締まる手続き。逮捕や刑罰が目的。
あなたが暴行を振るったり、金品を盗んだりしていない限り、警察が動く可能性はほぼありません。「お客様を怒らせた罪」という法律は存在しないからです。
相手が「警察に行く」と言動した場合も、「どうぞ、行ってください」と冷静に回答して問題ありません。多くの場合、警察は興奮するクレーマーを諌め、企業側の味方になってくれます。
逆に企業側から「強要罪」「脅迫罪」で訴追できるリスク
視点を変えましょう。理不尽な要求を盾に「訴えるぞ」と脅す行為は、逆に相手側が犯罪者になる可能性をはらんでいます。
もし、相手が以下のような発言をしていれば、刑法に触れる可能性があります。
- 強要罪(刑法223条): 「土下座しろ! さもなくば訴えるぞ」「〇〇しないなら会社に乗り込むぞ」など、威圧的な言動で強要する行為
- 脅迫罪(刑法222条): 危害を加えることを示唆する発言
- 業務妨害罪(刑法234条): 長時間にわたる拘束や大声でわめき散らし、業務に支障をきたす行為
今の状況は訴えられるかもしれないと怯える場面ではありません。むしろ「これ以上続けるなら、こちらが法的措置を取りますよ」と警告できる、攻めに転じる場面です。この「攻守逆転」の視点を持つだけで、現場の心理的な余裕は大きく変わります。
カスハラ・クレーム対応に
お悩みの方は
お気軽にご相談ください
経営者様・会社様専門の相談窓口となっております
【ケース別】カスハラ相手の主張に「法的根拠」はあるか?勝敗ラインの判定

「脅しがハッタリなのはわかった。でも、少しでも自社に問題があったらどうしよう……」
この不安こそが現場のリアルです。よく発生するトラブル事例を法律と照らし合わせ、「これをしたら負け」「ここまではOK」という境界線(勝敗ライン)を明確にします。
ケース1|「入店拒否・退去命令」は人権侵害か?
「俺は顧客だぞ! 入店拒否なんて差別だ!」大声を出したり、長時間居座ったりする客に対し、退去を求めた際によく言われる言動です。
結論:正当な理由がある入店拒否や退去命令は「合法」であり、人権侵害にはなりません。
企業には「契約自由の原則」がある
企業(店舗)と顧客の関係は契約です。店員側にも「誰と契約するか(誰を客にするか)」を選ぶ自由があります(契約自由の原則)。
人種や信条を理由とした不当な差別は禁止ですが、以下のような迷惑行為を理由とするケースは、店舗側の「施設管理権」の行使として完全に正当です。
- 大声を出して他の客に迷惑行為を及ぼす
- 従業員に暴言を吐く、威圧的な要求をする
- 長時間何も注文せずに拘束する
相手が「客」としてのルールを守らない以上、毅然と退去を求めてください。
ケース2|「体に触れた・腕を掴んだ」は暴行罪になるか?
「おい、今俺に触ったな? 暴行罪で訴えるぞ!」暴れる客を制止しようとして体に触れてしまった時、これを盾に取られる事案があります。
結論:状況によりますが、「正当防衛」や「正当業務行為」が認められる可能性がほとんどです。
相手を殴ったり怪我をさせれば「過剰防衛」ですが、以下のような防衛的な行為であれば違法性は否定されます。
- 殴りかかってきた相手の腕を掴んで止めた
- 立ち入り禁止区域に入ろうとした顧客を前に押し戻した
- 他の客や商品に損害を与えそうになったので、体を押さえた
重要なのは、「攻撃」ではなく「守る・止める」ためであったか、そして「必要最小限の力であったか」という判断です。防犯カメラの映像や録音などの証拠データがあれば、やむを得ない措置だったと証明でき、企業側が罪に問われる可能性はまずありません。
ケース3|「SNSに実名を晒す」は名誉毀損か?
「お前の名前と顔、SNSに晒してやるからな! 事実を書いて何が悪い!」店員に男性がスマホを向け、このような言動で脅迫するケースも増加しています。
重要な法知識:「事実であっても名誉毀損は成立する」ということです。
「公益性」がない暴露は違法
刑法上の名誉毀損罪は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した」場合に成立します。「本当のことだから書いていい」という理屈は通用しません。
「政治家の汚職」のような公共の利益に関わる問題(公益性)は例外ですが、「店員の態度が気に入らない」という私的な不満に公益性は認められません。
実際にSNSで晒され、企業が損害を被った場合は、逆にこちらから以下の法的手段を取るべきです。
- プライバシー権侵害による削除請求
- 発信者情報開示請求(投稿者の特定)
- 名誉毀損・業務妨害での損害賠償請求
相手が「拡散するぞ」と発言してきたら、「名誉毀損・業務妨害に当たる可能性が高いため、投稿された場合は法的措置を検討します」と冷静に通報することが最大の防御対策です。
ケース4|不当なキャンセル料・違約金請求は有効か?
最近増加しているのが、顧客側が「不当なキャンセル料を請求された」「契約を解除するのに違約金を求められた」と主張し、逆に企業を訴訟するケースです。これは取引先との問題でも発生します。
結論:利用規約や約款に明確に記載されていれば、企業側の主張は有効です。
重要なのは、「規約の存在」と「顧客がそれを認識していたか」の証拠です。契約時に規約を交付したり、ウェブサイトに明記したりする記録を残しておくことが必要です。
客側が「知らなかった」と主張しても、規約が社会通念上合理的な範囲内であれば、裁判所は企業側の正当性を認めることがほとんどです。
カスハラ・クレーム対応に
お悩みの方は
お気軽にご相談ください
経営者様・会社様専門の相談窓口となっております
カスハラ客から訴えられた場合の初動マニュアル

クレームの主張の法的根拠がいかに乏しいかを知っても、本当に訴訟を起こしてくる悪質な客はゼロではありません。
特に「内容証明郵便」や「裁判所からの特別送達」が届いた場合、それは単なる脅しではなく、企業にとって最も警戒すべきフェーズに移行したことを意味します。
この段階で初動を誤ると、正当な対応をしていたにもかかわらず、手続き上のミスで敗訴するリスクがあります。以下の3ステップを迅速かつ正確に実施してください。
ステップ1|絶対に無視しない(無視=欠席敗訴)
裁判所から届く「訴状」や、弁護士からの「内容証明郵便」は、決して放置してはいけません。
訴訟に記載された「第1回口頭弁論期日」までに「答弁書」を提出し、出廷しなければ、一方的に相手(クレーマー)の主張を全て認めたと見なされ、欠席裁判で敗訴が確定します。
【現場担当者への重要ポイント】
- 訴状が届いたら、中身を読まずに即座に法務担当者または経営層へ報告!
- 答弁書の期限:裁判所からの指定期日(口頭弁論期日)の原則1週間前までに提出が必要です。この時間的期限を厳守しないと、弁護士でも取り返しがつかなくなる可能性があります。
- 内容証明郵便も同様に、指定された期日(通常1週間〜10日程度)までに「反論の意思を示す」文書を作成し、返送することが必要です。
内容を読んで感情的にならず、「法的文書が届いた」という事実のみに注目し、冷静に手続きの準備を始めることが最優先です。
ステップ2|最優先で証拠の保全と時系列の整理を行う
法的紛争は、「客観的な証拠データに裏打ちされているか」で勝敗が判断されます。「言った言わない」の記録では、正当性を証明することはできません。
訴訟や内容証明が届いた時点で、トラブル発生時のあらゆる証拠を体系的に確保し、時系列で整理してください。
最優先で確保すべき証拠リスト
- 映像・音声記録|防犯カメラの撮影、電話録音データ(時間が過ぎると自動消去される可能性があるため最優先)。
- 対応記録|担当職員、責任者が記録した詳細な日報、社内メールのやり取り。
- 目撃者|現場に居合わせた従業員、他のお客様の証言内容(メモ書き)。
- 関連文書|相手から届いたSNSやメールのスクリーンショット、修理・交換の記録、相手の電話番号や発信元情報。
証拠は鮮度が命です。特にデジタルデータはすぐに消える可能性があるため、すぐにバックアップを取り、厳重に調査・管理してください。
ステップ3|現場判断での謝罪・金銭交渉は一切禁止
「面倒だから少額の金銭を払って解決にしよう」「とりあえず謝罪して収めよう」と現場担当者が判断することは極めて危険です。
謝罪・示談が不利になる理由
- 事実認定の固定化:謝罪文や和解書に署名すると、「企業側が落ち度を認めた」という事実が固定化され、後の訴訟で反論が難しくなります。
- 悪質客の味を占めさせる:一度でも金銭を払うと、「この会社は脅しで金が出る」と悪質な客に認識され、再度のクレームや他の悪質客への情報流出につながります。
書類が届いたら、必ず窓口を法務担当者または弁護士に一本化し、「以後の対応は全て専門家に一任しました」と従業員に伝えるよう徹底してください。現場の判断で相手に連絡を取ったり、金銭的な約束をしたりする行動は厳禁です。
専門家への相談タイミングと費用の概算
訴訟が届いた場合、すぐに顧問弁護士または法律事務所に相談すべきです。専門家に依頼する場合、以下の費用がかかります。
| 項目 | 概算相場(民事訴訟対応の場合) | 備考 |
|---|---|---|
| 法律相談料 | 1時間 5,000円〜1万円 (初回無料の事務所も多数) | まずは状況を把握し、法的リスクを判断してもらう。 |
| 着手金 | 20万円〜50万円程度 (請求額による) | 訴訟対応に着手する際に支払う費用。 |
| 報酬金 | 訴訟に勝利した場合に発生する成功報酬。 | 敗訴した場合は原則不要。 |
事前の顧問弁護士契約があれば、着手金や相談料が大幅に抑えられ、緊急時の負担が軽減されます。
カスハラ・クレーム対応に
お悩みの方は
お気軽にご相談ください
経営者様・会社様専門の相談窓口となっております
二度と従業員を危険に晒さないために!カスハラから組織としての「守り」を固める

目の前のトラブル対応も重要ですが、最も大切なのは、「あの時、会社が守ってくれた」と労働者が心から思える体制を築き、組織全体の耐性を高めることです。
これは、社員の安全配慮義務を果たすとともに、離職を防ぎ、ひいては企業ブランドを守るための、経営戦略です。
現場任せにしない「カスハラ対応マニュアル」の作成
トラブル時の判断を個人に委ねると、過度な負担と対応ムラによるリスクが生じます。
「ここからは毅然と対応する」という明確なルール(レッドライン)を組織全体で共有することが不可欠です。
- 対応のゴール設定: 謝罪や要求受諾ではなく、「問題の切り分け」と「従業員の安全確保」を最優先ゴールとする
- 警察通報の基準: 暴言・暴行・大声・長時間拘束など、「〇〇が起きたら通報する」という基準を明確化し、現場の迷いをなくす
- 権限移譲の明確化: 責任者、法務、警察へ「いつ、誰が」バトンタッチするのかを定式化する
マニュアルがあることで、従業員は「会社のルールに従って行動している」という確信と、精神的な安心感を持つことができます。
安全配慮義務と厚生労働省の指針
カスハラ対策は、労働者の安全配慮義務違反に問われないための必要な業務です。
厚生労働省は、カスタマーハラスメントへの対策を企業に実施するよう強く求めており、職場でのハラスメント(セクハラ等を含む)防止対策の一環として、相談窓口の設置などを定義しています。
今後、安全配慮義務違反による損害賠償請求の事例が増加する可能性があるため、組織的な体制づくりは急務です。
メンタルヘルスケアの義務と体制構築
カスハラ対応は、対応者にとって肉体的・精神的に極めて大きな負担がかかります。訴訟の脅迫を受けた職員を放置することは、安全配慮義務違反となるリスクも孕んでいます。
- 緊急ケア:トラブル直後の担当者に対し、必ず業務から切り離し、休憩とカウンセリングの機会を設置する
- 組織的フォロー:「あなたの対応は間違っていない」と責任者から明確に伝え、会社全体で守る姿勢を示す
- 相談窓口の周知: 社内の相談窓口(産業医や外部のEAPサービス)を周知徹底し、ストレスを抱え込ませない仕組みを作成する
従業員の心の健康を確保することこそが、結果として離職率の低下と安定した業務運営につながります。
法的措置を辞さない「毅然とした姿勢」を表明
悪質なクレーマーは、「この会社なら付け込める」と判断して行動を起こします。その「隙」を最初から与えないための抑止力が必要です。
店舗やウェブサイト、電話応対時の自動音声などで、カスハラに対する会社の明確な方針を説明し、宣言しましょう。
「従業員への暴言、ハラスメント行為(セクハラ等)、または不当な金銭要求があった場合、当社は即座に警察へ通報し、法的手段(損害賠償請求等)を検討し、辞さない姿勢で臨みます。」
この姿勢は、悪質な客に対して「うちの会社は甘くない」というメッセージを事前伝達する、強力な防衛手段です。そして何より、従業員に対する「会社は必ずあなたたちを守る」という、最も心強いメッセージになります。
顧問弁護士との連携体制
訴訟対応や内容証明への反論書作成は、専門知識がないと非常に困難です。また、初動の数時間〜数日間が勝敗を分けることもあります。
トラブル発生時の相談先を平時から確保しておくことは、最高レベルの危機管理です。
- 迅速な対応:緊急時に即座に法的アドバイスを受けられる体制を整え、初動のミスを防ぐ
- コスト削減:悪質クレーマーとの交渉を顧問弁護士に一任することで、従業員の時間的・精神的負担を大幅に削減できる
- 解決の実現:弁護士が窓口になることで、理不尽な要求への回答や謝罪を拒否し、迅速な解決を実現します
トラブルが起きてから慌てて探すのではなく、平時から顧問弁護士や専門の相談窓口と連携しておくことが、あなたの企業と労働者を守る最大の「お守り」になります。
カスハラ・クレーム対応に
お悩みの方は
お気軽にご相談ください
経営者様・会社様専門の相談窓口となっております
まとめ|理不尽な訴えには屈しない。正しい知識が会社と従業員を救う

ここまで、カスハラ客の「訴えてやる」という脅迫にどう対処すべきか、法的な視点から具体的な行動までを解説してきました。
この記事であなたが持ち帰るべき最も重要な結論を再確認しましょう。
ほとんどの「訴訟の脅し」は法的根拠のないハッタリである
理不尽な要求を盾に「訴えてやる」と叫ぶ行為は、そのほとんどが「恐怖を与え、無理やり要求を通す」ための心理的戦略です。法的な裏付けがない事案が多いため、過度に怯える必要はありません。
ただし、準備を怠れば、ハッタリでも負けるリスクがある。
万が一、訴訟や内容証明といった法的文書が届いた場合、それは「準備の有無」を試す試験です。この時、あなたが冷静に「証拠を保全し、弁護士に相談する」という正しい初動マニュアルを持っていれば、相手のハッタリは完全に通用しなくなります。
毅然とした対応は「お客様の奴隷」になることを拒否する意思表示
不当な要求に毅然と対応する必要があるのは、従業員の安全と、善良な顧客へのサービスを守るためです。
不当な要求を一方的に受け入れると、「この企業は脅しで通る」という前例を作り、悪質なクレーマーの再来を許すことになります。これでは、真面目に働く労働者が疲弊し、本来大切にすべき顧客へのサービスが低下します。
毅然と戦う行動は、単なる防御ではありません。それは、「私たちはプロフェッショナルであり、不当な行為には屈しない」という企業倫理を全うする、最も誠実な回答なのです。
不安を確実に解消する体制づくりが必要
現場スタッフが安心して働くために、次の行動に移りましょう。
- カスハラ対策マニュアルの作成:まずは無料テンプレートなどを活用し、「どこから警察を呼ぶか」の明確なレッドラインを作成しましょう。
- 専門家への相談:費用対効果を考え、「自社の対応は法的に正しかったのか?」「あの時の録音データは証拠になるか?」といった不安は、プロに聞くのが一番確実です。
- 弁護士連携の強化:顧問弁護士や弁護士保険の体制を整え、「いざという時、会社が必ず守ってくれる」という安心感を従業員に与えましょう。
理不尽な訴えに屈することなく、正しい知識と備えで、従業員と企業ブランドを守り抜いてください。
香川総合法律事務所では、カスハラ顧客やクレーム顧客の対応をはじめ、企業向けのカスハラマニュアルの作成や、研修等も行なっております。カスハラやクレームにお困りの場合は、是非ご相談ください。
カスハラ・クレーム対応に
お悩みの方は
お気軽にご相談ください
経営者様・会社様専門の相談窓口となっております