本記事では、ペイシェントハラスメント(病院でのカスタマーハラスメントを指す。以下「ペイハラ」という。)を理由に診療を拒絶したことについて、札幌地方裁判所の判決を例に、そこから読み取れるペイハラへの備えについて解説する。
事件の概要
この判例は、医師の応召義務は絶対的なものではなく、患者の著しい迷惑行為や、それによる信頼関係の喪失があれば、診療拒否が「正当な事由」として認められ得ることを示している。
医療現場におけるペイハラは他分野のカスハラと異なり、応召義務の存在や生命に関わる緊急性が争点となり得ることから、係争への発展リスクが高いと言える。係争に発展した場合に備え、ペイハラに直面した際は、本件のように、他の患者やスタッフに危害が及ぶ可能性がある、治療に必要な信頼関係が完全に失われているといった、「正当な事由」となり得る客観的な事実をチーム内で共有し、具体的に記録として残していくことが重要である。

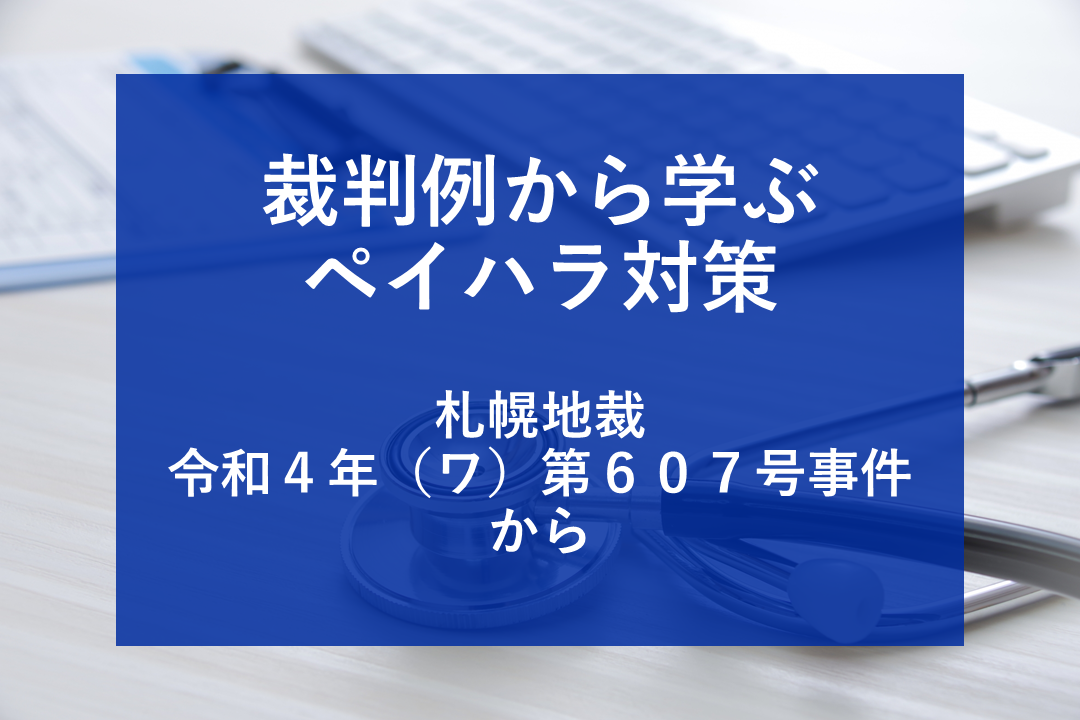
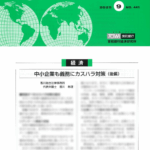

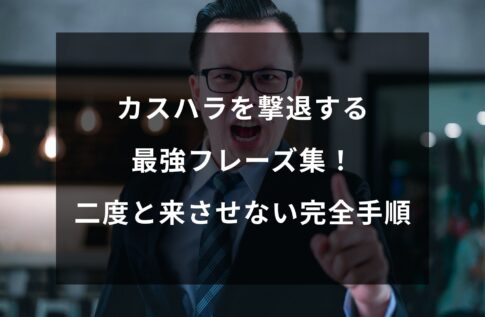
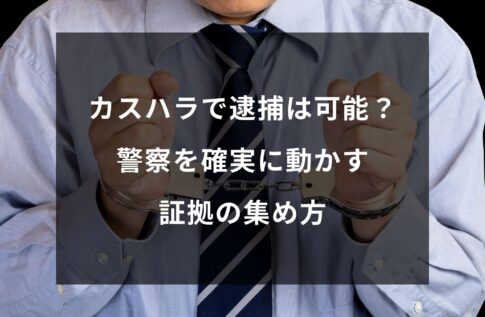
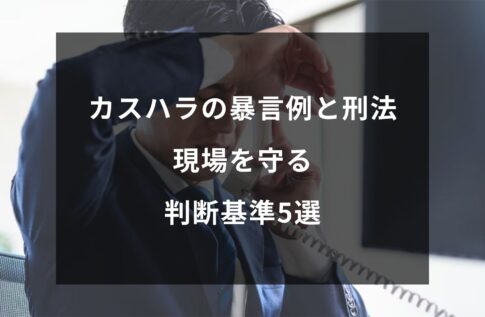
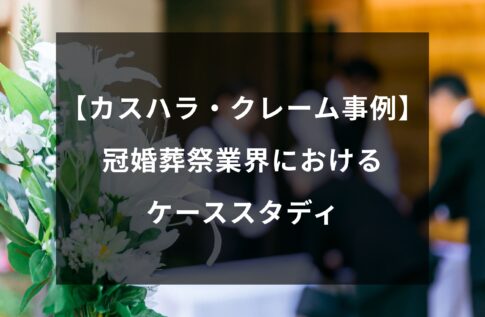
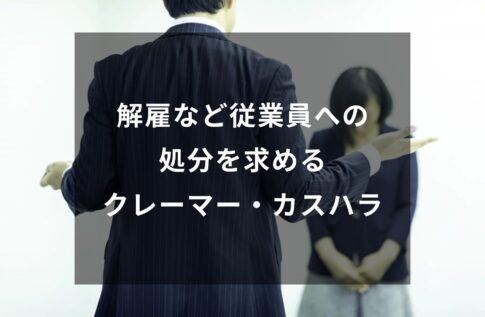
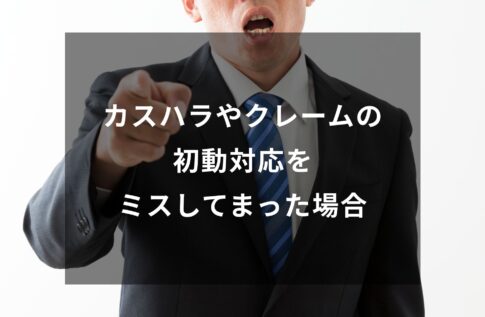

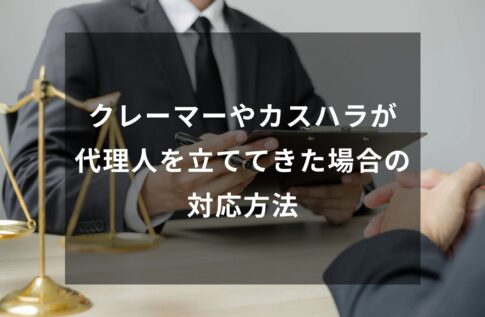
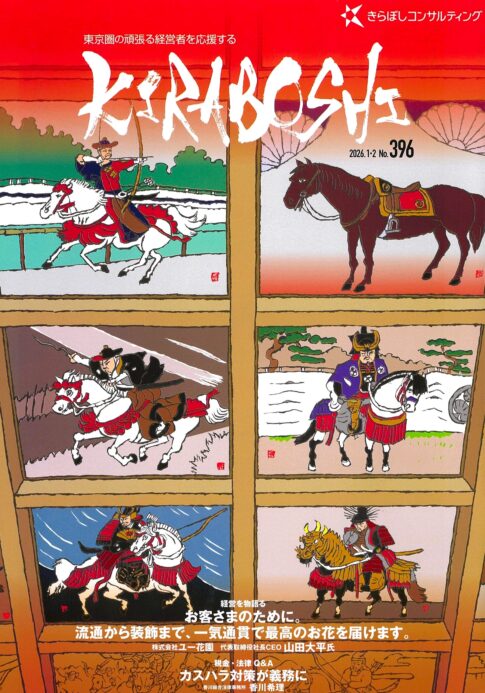

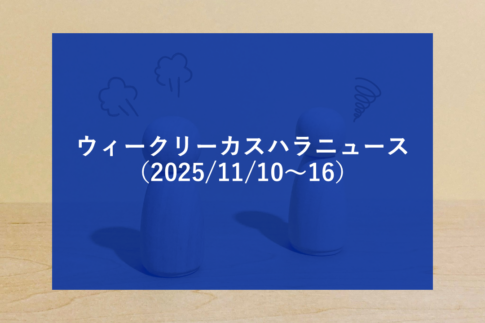
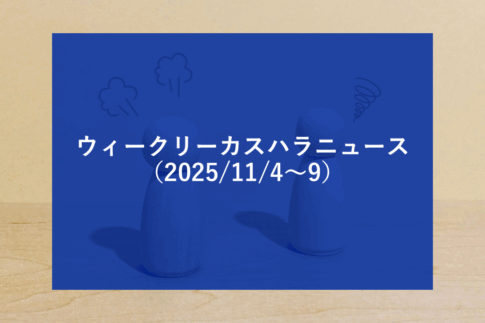
札幌地方裁判所令和4年(ワ)607号 損害賠償請求事件
令和5年4月26日 判決
《認定事実概要》
原告は、動悸と嘔気を訴え被告の勤務する病院に救急搬送され、当直業務を担当としていた被告(以下A医師)が診療に当たった。A医師は、原告が搬送される前に、過去のカルテから男性不信やPTSDの既往歴を確認していた。
A医師が問診後、原告に対し心エコー検査を行う旨説明をしたところ、原告は突然「なぜ男性医師がやる必要があるのですか。信じられない。看護師さんの業務範囲じゃないんですか」と大声で激高し、男性であるA医師による心エコー検査を激しく拒絶した。A医師が心エコー検査が看護師の業務でないことを説明しても「そんなの信じられない」と大声を出すなどしたため、女性看護師が心電図検査を行ったが、同検査では異常は認められなかった。
A医師は原告の夫に対し、被告病院において女性スタッフの常駐と精神症状への対応が不可能であり、基本的には精神疾患も診られる病院に搬送した方が良いと思うこと、今後同様の症状で被告病院を受診しても、検査を拒否する以上、責任ある診断ができないこと等を説明した。
その後、ベッド移動のために原告に声を掛けた男性看護師に対し、原告は「大声を出さないでください。医療者の方が上なんですか。」などと激高し、なだめに入った原告の夫に暴行を加え罵声を浴びせるなどし、他の患者が休んでいるので静かにするよう説明しても大声は変わらなかった。
原告は夫を介しA医師に対して点滴を要望したところ、A医師は「一方的な希望のみで点滴治療はできない、しかるべき病院を受診して必要な診療を受けてください、信頼関係が築けていない中で治療を行っても後々本人のためにならない」などと答えた。原告は、再び大声を上げて不満を訴え、帰宅を促す原告の夫に暴行を加えた。
A医師が、原告が帰らない場合には警察に相談させてもらうことになる旨を看護師を介して告げるなどしたところ、原告らは被告病院を立ち去った。
《原告の主張》
原告は、治療行為に対し抗議をした事実はあるが、苦しんでいたのであって、不要な検査を拒んだところ以後の治療を拒否されれば、語気が荒くなっても無理はない。原告の抗議は、不当な治療拒否に対する正当な権利主張である。
また、夫に暴行を加えた事実は無く、仮にあったとしても夫婦間の問題であり、A医師が治療を拒絶することとは関係が無い。
A医師が、精神科の受診を強要し、治療を拒否し、原告を放置したことは、医師法19条1項(※)の趣旨に照らし、社会通念上、認められる行為ではない。
このような対応により、きわめて大きな精神的苦痛を受けたのであるから、慰謝料として150万円が相当である。
※医師法 19条1項 診療に従事する医師は、診察治療の求があった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。
《被告の主張》
原告の症状を踏まえて必要な検査及び精神科の受診を勧めているのであって、適切な診療を提供している。
診療が継続できなかった原因は、原告が検査を拒否したことによる。また、原告は、原告が希望していた点滴治療を受けられなかったことをもって、診療拒絶があったと主張しているにすぎず、診療の内容を決定するのは医師であり、患者の希望どおりの診療を行う義務はない。
患者の迷惑行為が認められ、医療機関との信頼関係が喪失している場合には、医師法 19条1項の「正当な事由」があると解される。原告の言動は明らかに被告病院に対する迷惑行為である上、既にコミュニケーションを取れる状態にはなく、信頼関係が喪失していたといえるから、診察を拒絶する「正当な事由」が認められる。
《裁判所の判断》
〈争点について〉
医師による診療拒否が不法行為に当たるか否かは、医師法19条1項の趣旨を踏まえて社会通念に照らして判断されるべきである。心電図検査に異常は認められなかったことからすると、被告病院において、原告が訴える症状に対して緊急性は認められず、本件全証拠によっても点滴治療を行う必要性も認めがたい。
また、心エコー検査を行う旨を説明した際大声で激高したことから、精神疾患も診ることのできる病院に搬送依頼をしたほうが良い旨伝えたことには相応の理由が認められる。
そして、帰宅を促す原告に暴行を加える等、興奮状態となっていたから、この段階に至っては、原告に冷静な対応を求めることができないことは明らかであり、また、原告のこれらの言動は、被告病院に対する著しい迷惑行為となっていたことからすると、A医師が、治療を行うために必要な医師と患者との信頼関係を築くことができないと判断して、それ以上の診療を拒絶したことは、医師法19条1項の趣旨を踏まえても社会通念上相当であったといえる。
したがって、A医師は、違法に原告の診療を拒否したとはいえず、不法行為が成立するとは認められない。
〈結論〉
よって、原告の請求には理由がないから、これを棄却する。